子どもの受験が近づいてくると、急に気になりだす「内申点」。
実は私も昔は「テストの点数さえ良ければ大丈夫でしょ?」なんて思っていたクチなんです。
でも塾の先生から「それじゃダメ!」とバッサリ。
ぶっちゃけ親子でこんな風に思ってました(;^_^A
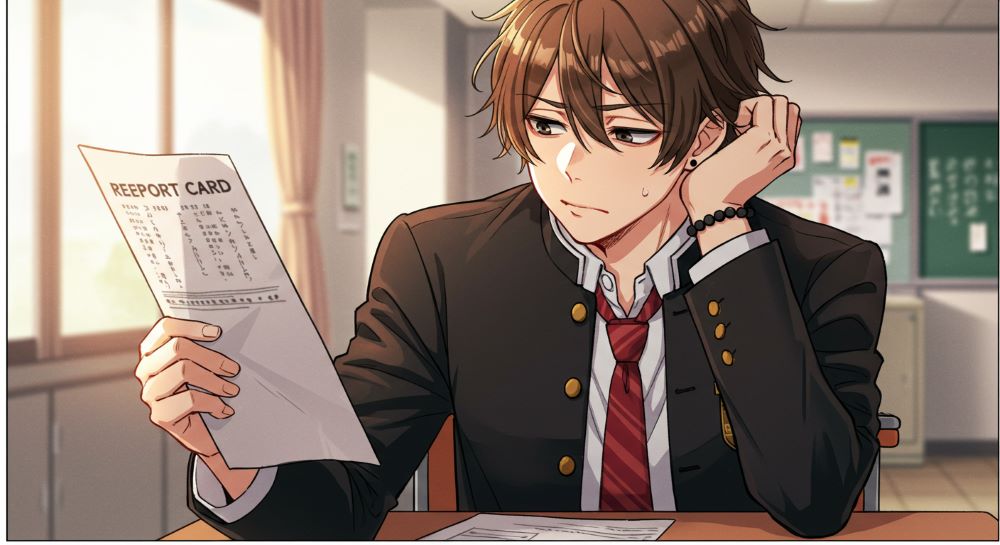
でも、塾の先生に甘いとバッサリ・・・(;^_^A
そこで教えてもらった内申点アップの秘訣を実践したら、全然上がらなかったうちの子の内申点が上がったんです!
今日はその体験を元に、誰でも実践できる内申点アップ法をお伝えします♪
内申点とは?知らないと損する3つの基礎知識
「内申点って何?」と思っていませんか?私も最初はそうでした!
内申点は高校受験での合否を左右する超重要なポイントなんです。
塾の先生に「内申書は先生からの推薦状みたいなもの」と教えてもらって初めて重要性に気づきました。
日頃の学校生活の評価が数字になって、受験に大きく影響するなんて知らなかった…。
これを知らずに対策しないなんてもったいない!
あなたもぜひ基本から押さえていきましょう。
内申点が高校受験の合否を左右する決定的理由とは
内申点、侮れないんですよ~!うちの子の通っていた塾では「内申点は受験の半分以上を占める場合もある」って言われてたんです。実際、都道府県によって違いますが、公立高校では内申点と入試の点数の比率が「5:5」とか「7:3」なんてことも!
うちの県では、50%が内申点で評価されます。
なので、ほぼ内申で高校が決まるといっても過言ではないのです!(;^_^A
私が驚いたのは、同じテストの点数でも内申点の差で合否が分かれるケースがあるということ。
だから「あの子より点数良かったのに…」なんてことにならないためにも、内申点対策は必須なんです。
「学校の先生に気に入られればいいの?」なんて思ってない?
なんとなくありそうですが・・・(;^_^A
実は内申点には明確な評価基準があるんです!
塾で教わった時、目から鱗が落ちた気分でした。
▼内申点の重要ポイント▼
・高校によっては募集定員の一部を内申点だけで決める場合も
・推薦入試では内申点が決め手になる
・同点の場合、内申点で優先順位が決まることが多い
学校の先生も教えてくれない、こんな大事なことを知らないなんてもったいなさすぎますよね!
私も知ってから「もっと早く対策すればよかった…」と後悔しました。でも大丈夫!今からでも十分間に合います♪
学校別・教科別の評定はどう決まる?先生の評価基準を徹底解説
「先生の主観で決まるんじゃないの?」って思ってました?
実はそうじゃないんです!
塾の先生から教えてもらった時はビックリ!評定には意外とちゃんとした基準があるんですよ。
学校によって若干の違いはありますが、基本的には次の3つの観点から評価されます。
- 知識・技能(テストの点数など)
- 思考力・判断力・表現力(発言や提出物の内容)
- 学びに向かう力・人間性(授業態度や提出状況)
「え?テストだけじゃないの?」って驚きましたか?
私も最初は驚きました!実は学校の先生たち、私たちが思っている以上にいろんなところを見ているんです。
塾の先生が教えてくれたのは、「定期テストの点数は評価の30~40%程度」ということ。
(これは県や学校単位で違うのであくまで参考程度でお願いします)
残りは授業中の様子や提出物、発言の内容などから総合的に判断されるんですって。
これ、知らないと損ですよね!
「じゃあ、どうすれば評価が上がるの?」って思いますよね。
私も同じことを塾の先生に尋ねました。
すると「小さなことの積み重ねが大事」と教えてくれたんです。
例えば、国語なら発言の内容や読解力、自分の意見をしっかり持っているかが見られています。
数学では解き方の工夫や粘り強さ、理科では観察力や実験への取り組み姿勢なども評価対象に。
「そんなの全部完ぺきにできないよ~」って思いますよね?大丈夫です!
うちの子も最初はそうでした。でも少しずつ意識して取り組むだけで、評定は上がっていきますよ。
私が塾で教わった「各教科の評価ポイント」を実践したら、特に苦手だった理科の内申が「3」から「4」に上がったんですから!
評定で「2」がついている人は、まずは生活態度から改めるべき。
こちらを参考に、オール3までは上げましょう!
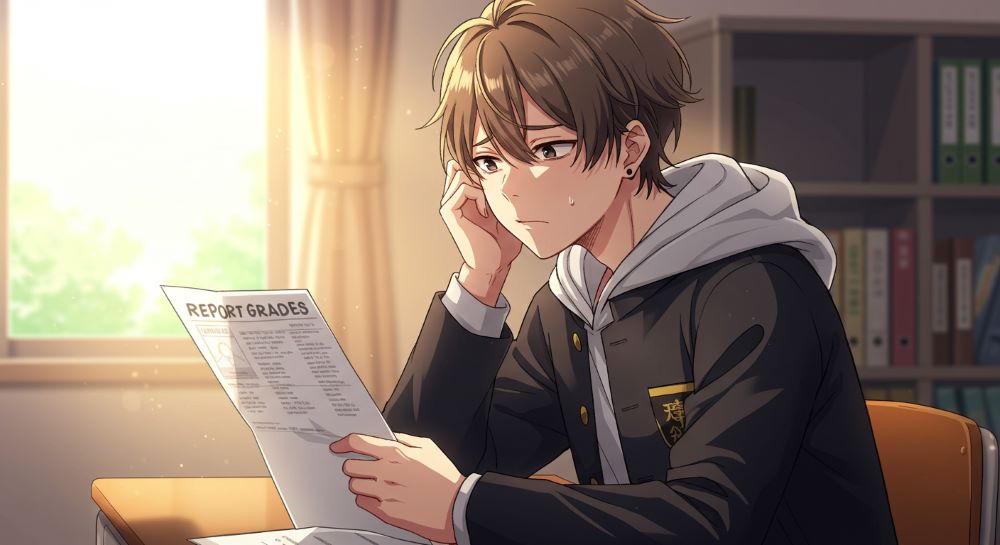
通知表と内申書の違い—知っておくべき重要ポイント
「通知表と内申書って同じじゃないの?」って思ってませんか?
実は違うんです!これ、私も塾に相談するまで知らなくて、かなり焦りました(;^_^A
通知表は学期ごとの評価で、保護者向けに子どもの学習状況を伝えるためのもの。
一方、内申書(調査書)は高校受験のために作成される公式文書なんです。
私が塾の先生から教えてもらって驚いたのは、通知表の「3」と内申書の「3」は微妙に違うこともあるということ!学校によっては、通知表は相対評価で、内申書は絶対評価というケースもあるんです。
「じゃあ、どっちを気にすればいいの?」って思いますよね。両方大事なんですが、受験直前になると修正が難しくなるので、早めの対策が必要なんです。
実はうちの子、中学2年の後半まで通知表ばかり気にして内申対策をしていなかったんです。塾の先生に「内申書と通知表は違う」と教えてもらってから、慌てて対策を始めました。結果的には間に合いましたが、もっと早く知っていればもっと余裕をもって対策できたのにな~と思います。
まずは今もらっている通知表の評価基準を確認してみてください。担任の先生に「内申点との関係はどうなっていますか?」と聞いてみるのも良いですよ。うちの子の学校では、先生が丁寧に説明してくれました。
今すぐ実践!内申点アップの即効テクニック7選
「内申点の仕組みはわかったけど、具体的に何をすればいいの?」って思いますよね。
私も最初はそうでした!塾の先生に相談したところ、すぐに実践できる効果的な方法を教えてもらいました。
実は小さな工夫の積み重ねが大きな違いを生むんです!うちの子も「えー、こんなことで?」と半信半疑でしたが、実践してみたら見事に内申点がアップ!今日からでも始められる即効テクニックをご紹介します♪
テストで確実に得点を上げる科目別勉強法のコツ
「テストの点数を上げるのは当たり前じゃない?」って思いますよね。でも実は、ただ点数を上げるだけじゃなく、先生に「伸びている」と思ってもらうことが大切なんです!
塾で教えてもらったのは、「前回より10点アップ」を目指す方が、「いきなり90点」を目指すより効果的だということ。特に苦手科目は、少しでも上がれば先生は「頑張っている」と評価してくれるんですよ。
うちの子は数学が苦手で、いつも50点前後。でも塾の先生のアドバイスで「簡単な問題を確実に解く」戦略に切り替えたら、次のテストで65点に!先生からも「頑張ったね」と声をかけてもらえました。
科目別のコツとしては、例えば国語は記述問題を丁寧に書く、数学は解答過程をきれいに書く、英語は単語テストで満点を取るなど、先生が見るポイントを押さえることが大事です。
◇テスト対策のポイント◇
・前回のテストの間違いを必ず見直す ・授業中に先生が強調した部分を重点的に ・ノートの内容をテスト前に確認する
私の失敗談ですが、最初は「テストだけ対策すればいい」と思っていたんです。でも実は日々の小テストや提出物も評価に含まれていたんですよね。これを知ってからは小テストも真剣に取り組むようにしたら、理科と社会の内申が上がりました!
「テスト前だけ頑張る」よりも、「コツコツと積み重ねる」方が内申点アップには効果的ですよ。あなたのお子さんも、明日からの小テストから気をつけてみてはいかがでしょうか?
提出物で高評価をもらう「期限厳守」の黄金ルール
提出物の期限守ってますか?「ちょっと遅れても大したことないよね」なんて思ってない?
これが実は内申点に大きく影響するんです!私も「宿題の質が良ければ少し遅れても…」なんて甘く考えていたのですが、塾の先生から「それは大間違い!」と厳しく指摘されました。
塾の先生が教えてくれたのは「提出期限を守ることは社会人としての基本的なスキル」だということ。
先生たちは単に宿題の内容だけでなく、責任感や時間管理能力も見ているんですって。
うちの子は創作が好きで、国語のレポートなどは内容にこだわりすぎて提出が遅れがちでした。
でも「期限内に出す」ことを最優先にしたら、評価が上がったんです!
★提出物の黄金ルール★ ・期限より1日前に完成させる ・提出日をカレンダーに書き込む ・難しい課題は早めに取り掛かる
「でも忘れちゃうんだよね~」というお子さんには、スマホのリマインダー機能を活用するのもおすすめ。うちの子も部活で疲れて忘れがちだったので、リマインダーをセットしたら忘れ物が激減しました。
塾の先生から面白い話を聞いたんですが、ある学校の先生は「提出期限を守った生徒」と「内容が素晴らしいけど遅れた生徒」では、前者の方が高評価をつけるそうです。社会に出てからも大切なスキルですよね。
提出物は「質」より先に「期限を守る」ことから始めてみてください。
うちの子はこれだけで英語と社会の内申が上がりましたよ!
教師の目に留まる!ノート術と提出物の工夫ポイント
「ノートなんて取り方は人それぞれでしょ?」なんて思ってませんか?
実はノートの取り方一つで内申点が変わることを、塾で知って驚きました!
先生たちはノートを見るとき、単に「書いてあるか」だけでなく「理解して整理できているか」を見ているんです。うちの子のノートを塾の先生に見せたら「これじゃ先生に伝わらない」と言われてしまいました。
そこで実践したのが「1ページを3分割」するノート術。上部に日付とテーマ、中央に授業内容、下部に自分の質問や気づきを書くようにしたんです。これだけで先生から「よくまとめているね」と言われるように!
■ノート術のコツ■ ・色分けは3色程度に抑える ・先生の言葉を「 」でそのまま書く ・図や表を活用して視覚的にまとめる
提出物も同じく工夫が必要です。例えば、レポートなら「起承転結」を意識する、資料集めをしっかりする、表紙をつけるなど、ちょっとした差が大きな評価の差につながります。
うちの子は理科が苦手でしたが、実験レポートに「気づいたこと」の欄を追加したら、先生に「よく観察しているね」と褒められました。内申点も「3」から「4」に上がったんですよ!
「でも字が汚いから…」って諦めてませんか?字が苦手なら、パソコンで作成するのもOK!うちの子も手書きが苦手でしたが、許可を得てパソコンで作成したレポートを提出したら高評価でした。もちろん、事前に先生に相談するのを忘れずに。
小さな工夫が大きな違いを生みます。明日のノートから意識して変えてみませんか?
授業中の発言で印象アップ!積極性をアピールする方法
「授業中に手を挙げるなんて恥ずかしい…」そう思っているお子さんも多いのでは?うちの子もそうでした。
でも実は、授業中の発言が内申点アップの近道だったんです!
塾の先生から聞いた衝撃の事実。「先生たちは発言する生徒の名前と内容を覚えている」んだそうです。特に中学校では30人以上のクラスで全員を細かく見るのは難しいから、発言する子が印象に残るんですって。
「でも間違えたら恥ずかしい…」それが心配なら、こんな方法はどうでしょう?うちの子が実践したのは、「わからないことを質問する」という方法。「答えを言う」より「質問する」方が、実はハードルが低いんです。
👉発言アップのコツ👉 ・「〇〇についてもう少し詳しく教えてください」 ・「〇〇と△△はどう違うんですか?」 ・「この問題の解き方が分からないので教えてください」
塾の先生が言っていたのは、「質問できる生徒は思考力がある証拠」だということ。間違いを恐れずに発言することで、「学ぶ意欲がある」と評価されるんです。
うちの子は英語の授業で「この単語の発音がわかりません」と質問したのをきっかけに、先生が話しかけてくれるようになりました。それから少しずつ発言できるようになり、英語の内申が「3」から「4」に上がったんですよ!
「でも本当に恥ずかしい…」というなら、授業の最初か最後に先生に近づいて個別に質問するのも効果的。人前で話すのが苦手でも、先生との関係は築けますよ。
明日の授業で、ぜひ一回だけでも手を挙げてみませんか?小さな一歩が、大きな変化を生みますよ!
自主学習ノートで「やる気」を見せる効果的なアプローチ
「自主学習ノート?面倒くさそう…」って思いませんでした?
私も最初はそう思っていたんです。でも塾の先生から「これは内申点アップの秘密兵器」と教えてもらって、試してみたらすごかった!
自主学習ノートとは、学校や塾から出された宿題とは別に、自分で計画を立てて学習するノートのこと。これが先生に「やる気がある」「自主性がある」というアピールになるんです。
うちの子は国語が苦手だったので、「今日の漢字5つ」というコーナーを作って毎日書いていました。最初は「意味あるの?」って言っていたのに、先生に「よく頑張ってるね」と言われてからは張り切って続けてましたよ。
◆自主学習ノートの作り方◆ ・表紙と学習計画を最初に書く ・日付は必ず入れる ・苦手科目を重点的に ・図やグラフを入れると見栄えアップ
塾の先生が強調していたのは「継続することが大事」ということ。内容が完璧でなくても、毎日少しずつでも続けることで評価されるんです。
実はこれ、提出のタイミングも重要なんですよ。定期テスト2週間前などの「先生が忙しくない時期」に提出すると、じっくり見てもらえるんです。うちの子は先生に「いつ提出すればいいですか?」と聞いて、アドバイスどおりのタイミングで出したら、国語の内申が上がりました!
「うちの子には難しそう…」と思いますか?大丈夫です!最初は1日5分、1ページだけでOK。うちの子も最初は「めんどくさい」と言っていましたが、「漢字5つだけでいいよ」と言ったら続けられました。少しずつ習慣になっていきますよ。
明日から始めてみませんか?学年末までにはきっと大きな変化が見られるはずです!
質問上手になって先生との関係を良好に保つテクニック
「先生に質問なんて、できる子だけでしょ?」なんて思っていませんか?実はそんなことないんです!質問は「わからない子」がするものではなく、「向上心がある子」がするものなんですよ。
塾で教えてもらったのは、「質問は内申点アップの極意」ということ。先生は質問してくる生徒に対して「学ぶ意欲がある」と高評価をつけやすいんだそうです。
でも「何を質問していいかわからない」というのがほとんどですよね。うちの子もそうでした。そこで実践したのが「授業の最後に3行まとめ」。その日の授業で理解できなかった部分を3行でメモして、それを質問のネタにするんです。
▽質問のコツ▽ ・「ここまでは理解できたけど、ここからがわかりません」と伝える ・授業中に先生が言った言葉を引用する ・質問の前に自分なりの答えを考えておく
「でも放課後、部活があって質問できない…」という場合は、朝の時間を活用するのもいいですね。うちの子は朝早く学校に行って、職員室前で待ち、先生が来たらさっと質問。「朝からやる気があるね」と評価が上がりました!
質問する内容も工夫が必要です。「全部わかりません」ではなく、「この部分がわからないので、ヒントをください」と言うと、先生も教えやすいんです。
うちの子は数学が特に苦手で、最初は質問もできませんでした。でも「今日の授業のどこがわからなかった?」と毎日聞いて、その部分を一緒に整理。それを翌日先生に質問するようにしたら、少しずつ理解が深まって、結果的に内申も上がりましたよ!
明日から、授業の最後に「わからなかったこと」をメモしてみませんか?それが質問のきっかけになりますよ。
担任・教科担当に直接アプローチ!面談での話し方と注意点
「先生と話すのって緊張する~」って思いますよね。私も最初は「何を話せばいいの?」ってドキドキしてました。でも塾の先生から面談のコツを教えてもらって実践したら、うちの子の内申点がアップしたんです!
三者面談や個人面談は、実は内申点アップの絶好のチャンス!この時間を有効活用することで、先生にあなたのお子さんの「頑張り」をしっかりアピールできるんです。
塾の先生が教えてくれた面談での話し方が、とても効果的でした。それは「具体的なエピソードと今後の目標をセットで伝える」こと。例えば「最近、数学の文章題が解けるようになって嬉しいです。次は証明問題も頑張りたいです」といった感じです。
♡面談で押さえるポイント♡ ・先生の話をメモする姿勢を見せる ・努力していることを具体的に伝える ・今後の課題と目標を自分から言う
特に効果的だったのは「先生のおかげで〇〇ができるようになりました」という感謝の言葉。うちの子は英語が苦手でしたが、面談で「先生の発音指導のおかげで単語が覚えやすくなりました」と伝えた後、英語の授業での発言機会が増えたんです!
ただし注意点も。「成績や内申点を直接上げてください」とお願いするのはNG!これは塾の先生から強く言われました。代わりに「どうすれば評価が上がるでしょうか?」と具体的なアドバイスを求める方が効果的です。
うちの子は中学2年の三者面談で、社会の先生から「歴史年表を作るといいよ」とアドバイスをもらい、実践したところ、次のテストで20点もアップ!内申も「3」から「4」に上がりました。
次の面談では、ぜひ「今、頑張っていること」と「これから頑張りたいこと」をセットで伝えてみてくださいね。先生との信頼関係が深まり、内申点アップにつながりますよ!
要注意!内申点を下げる8つのNG行動と対策法
「頑張っているのに内申点が上がらない…」そんなお悩みはありませんか?実はがんばりが報われない理由として、知らず知らずのうちに「内申点を下げる行動」をしているかもしれません!私も塾の先生に指摘されるまで気づかなかったんです。ちょっとした行動が内申点に大きく影響するんですよ。今日はそんな「やってはいけないこと」と対策法をお伝えします!
遅刻・欠席の記録が内申点に与える深刻な影響と挽回策
「少しくらいの遅刻や欠席は大丈夫でしょ?」…これ、大間違いなんです!塾の先生から「出席状況は内申点の大前提」と言われて驚きました。
実は遅刻・欠席の記録は、内申書に明確に記載される項目なんです。特に「無断欠席」や「理由のない遅刻」は大きなマイナスポイントに。うちの子が風邪で3日休んだ時、塾の先生に「登校したらすぐに課題を確認して取り組むこと」とアドバイスされ、実践したら先生からの印象が良くなりました。
「でも体調が悪い時もあるし…」そうですよね。病気や怪我での欠席はやむを得ません。大事なのは「その後のフォロー」なんです!
✓欠席後のフォロー法✓ ・休んだ日の授業内容を必ず確認する ・提出物の期限を確認して早めに提出 ・クラスメイトからノートを借りてコピーする
塾の先生が強調していたのは「事前連絡の重要性」。体調不良で休む場合も、朝一番に連絡することで印象が全然違うそうです。うちの子が部活の大会で早退する時も、前日に担任の先生に直接伝えておいたら、好印象だったみたいです。
「遅刻しそうになったらどうする?」という対策も教えてもらいました。少しでも遅れそうな場合は、保護者から連絡を入れること。そして登校したら必ず「遅れてすみません」と一言添えること。この小さな心遣いが評価につながるんですよ。
この対策を実践してから、うちの子の「生活の記録」の評価が上がりました。小さな習慣が大きな違いを生むんですね!明日からでもできることから始めてみませんか?
反抗的態度が評価を下げる理由と先生との信頼関係の築き方
「先生の言うことにいちいち反論しちゃダメなの?」って思いますよね。私も最初は「自分の意見を言うのは悪いことじゃない」と思っていました。でも塾の先生に「言い方と場所が重要」と教えてもらい、目からウロコでした!
実は反抗的な態度は「コミュニケーション能力の低さ」と判断されることがあるんです。特に授業中の「それは違うと思います」という言い方や、指示に対する「めんどくさい」というつぶやきは、思っている以上に評価を下げます。
うちの子は正義感が強くて、時々先生の説明に「それは違います」と言ってしまうことがありました。塾の先生に相談したところ、「まずは相手の意見を受け止めてから、自分の考えを伝える」という方法を教えてもらいました。
◎コミュニケーションの改善策◎ ・「なるほど、でも〇〇ということもあるのでは?」と提案調で ・授業中ではなく、授業後に個別に質問する ・「〇〇という理由で、私はこう思います」と根拠を示す
この方法を実践したら、先生からの印象がガラッと変わったんです!以前は「反抗的」と思われていたのが、「論理的に考える生徒」という評価に変わりました。
塾の先生が言っていたのは、「先生も人間だから、尊重されたいと思っている」ということ。先生に対する基本的な敬意を示すことで、信頼関係が築けるんです。
うちの子も、以前は「なんでこんなことするの?」と反抗的だった数学の先生に、「説明の仕方がわかりやすいです」と素直に伝えたら、その後の対応が変わったんですよ!内申点も「2」から「3」へアップしました。
「でも先生が間違っていることもあるよね?」そんな時はどうすればいいの?それは「質問形式」で伝えるのがコツ。「〇〇と教科書に書いてありますが、先生の説明と違うように感じました。どう理解すればいいですか?」というように。これなら先生も気分を害しません。
信頼関係は一日では築けませんが、小さな心遣いの積み重ねが大きな変化を生みます。明日から意識して試してみませんか?
提出物の遅れ・未提出がもたらす悪影響と挽回のチャンス
「宿題忘れちゃった…」「明日出せばいいや」なんて思っていませんか?これ、内申点に大きく響くんです!塾の先生から「提出物の遅れは最も評価を下げる要因の一つ」と聞いたときは本当にビックリ!
特に衝撃だったのは、「たとえ100点満点の内容でも、期限を過ぎると50点扱いになる学校もある」ということ。うちの子も提出物を忘れがちで、内申点に悩んでいました。
「でもどうすれば忘れずに出せるの?」という対策を塾の先生に聞いたところ、「提出物管理ノート」を作るようアドバイスをいただきました。
✓提出物管理のポイント✓ ・手帳やノートに提出物と期限を必ず書く ・前日に確認する習慣をつける ・友達と提出日を確認し合う
この方法を実践してから、うちの子の提出忘れがゼロになりました!先生からも「最近しっかりしてきたね」と言われて、自信がついたみたい。
「でも、もう提出し忘れちゃった…」という場合は?諦めないで!塾の先生が教えてくれた「挽回のチャンス」を紹介します。
まず、素直に謝ること。「忘れました」ではなく「責任を感じています。今からでも提出させていただけませんか?」と伝えると印象が違います。そして次回からは絶対に遅れないと約束すること。
うちの子は社会科のレポートを忘れてしまったとき、塾の先生のアドバイス通り「申し訳ありません。今日中に仕上げますので、見ていただけませんか?」と伝えたら、先生は「今日の放課後に持ってきなさい」と言ってくれました。その後、しっかり約束を守ったことで信頼関係が築けました。
「一度の失敗で全てが台無しになる」わけではありません。大切なのは、失敗したときの態度と、その後の行動です。ぜひ試してみてくださいね!
授業妨害と認定されるケースと気をつけるべきポイント
「おしゃべりくらいいいじゃない?」って思ってませんか?実は授業中の小さな行動が、先生からは「授業妨害」と見られていることがあるんです。これ、私も塾の先生に指摘されて初めて知りました!
内申点を大きく下げる「授業妨害」行為は、想像以上に幅広いんです。うちの子は「先生の話をしっかり聞く」ことはできていたんですが、ペンを回す癖があって、それが「授業に集中していない」と評価されていたことがありました。
塾の先生が教えてくれた「授業妨害と認定されがちな行動」リストを見てビックリ!
■授業妨害になりやすい行動■ ・友達と小声で話す ・授業と関係ないものをいじる ・居眠りする ・スマホを机の中で見る ・ため息をつく ・窓の外を見続ける
「えっ、そんなにたくさん?」と驚きですよね。私も最初は「厳しすぎない?」と思ったんです。でも塾の先生が「これらの行動は他の生徒の学習権も侵害している」と説明してくれて納得。
じゃあどうすればいいの?塾の先生のアドバイスは「意識的に良い姿勢を作ること」。具体的には「姿勢を正して、先生の目を見て、うなずきながら聞く」。これだけで先生からの評価が変わるんです!
うちの子も「先生の顔を見て、時々うなずく」ことを意識したら、数学の先生から「最近授業態度がいいね」と声をかけられました。内申点も上がったんですよ!
「でも90分も集中できない…」というのが本音ですよね。そんな時は「5分だけ集中」作戦がおすすめ。5分だけ完璧に集中して、また5分…と区切ると意外と乗り切れるんです。うちの子もこの方法で授業に集中できるようになりました。
明日の授業から、ぜひ「先生の目を見て、うなずく」ことを意識してみませんか?小さな行動変化が大きな評価アップにつながりますよ!
テスト前後の態度が評価を変える!成績不振時の正しい対応
「テストの点数が悪かった…」そんな時、あなたのお子さんはどんな反応をしていますか?実は点数だけでなく、その後の態度も内申点に影響するんです!これ、塾の先生から聞いて目からウロコでした。
うちの子は算数が苦手で、20点台のテスト結果に「もういいや…」と投げやりな態度になってしまうことがありました。塾の先生に相談すると「テスト後の姿勢こそが重要」と教えてもらいました。
特に効果的だったのは「リフレクションシート」の活用。テスト返却後に「できなかった問題」「なぜできなかったか」「次回に向けての対策」を書いて先生に提出するというもの。
◎テスト後の対応ポイント◎ ・テスト用紙の間違いに赤ペンで正解を書き込む ・わからない問題は必ず質問する ・次回の目標点数を具体的に設定する
うちの子がリフレクションシートを数学の先生に提出したら「しっかり反省できていますね」と言われました。次のテストでは10点アップ!内申点も少しずつ上がっていきましたよ。
「でも、テストの点数が悪いと落ち込むよね…」そうなんです。塾の先生が教えてくれたのは「短期的な目標設定」の大切さ。「90点を目指す」ではなく「前回より10点アップを目指す」ほうが達成感を得やすいんです。
また、テスト前の態度も重要!テスト1週間前から「先生、このプリントについて質問があります」など、積極的に準備している姿勢を見せると評価アップに。うちの子が英語のテスト前に単語の発音を個別に質問したら、先生との関係が良くなりました。
「テストでは結果が全て」ではありません。「結果が出なくても次に向けて努力する姿勢」が内申点アップのカギなんです。次のテストでぜひ試してみてくださいね!
グループワークで評価される3つの能力と発揮するコツ
「グループワークって苦手…」そんなお子さんも多いのでは?実はグループワークでの態度が内申点に大きく影響することを、塾の先生から教えてもらいました。特に「思考力・判断力・表現力」の評価につながりやすいんだそうです!
うちの子は内向的な性格で、最初はグループワークを嫌がっていました。でも塾の先生に「グループワークで評価される3つのポイント」を教えてもらい、実践したらみるみる評価が上がったんです。
📌グループワークの3つの評価ポイント📌 ・協働性:メンバーと協力して取り組めるか ・リーダーシップ:適切な意見や提案ができるか ・プレゼン力:自分の考えをわかりやすく伝えられるか
「でもうちの子は人見知りで…」大丈夫です!リーダーになる必要はありません。塾の先生が教えてくれたのは「得意な役割を見つける」こと。例えば、発表が苦手なら資料作りを担当するなど。
うちの子の場合は「記録係」を買って出るようにしました。みんなの意見をまとめるのが得意だったので、それを活かせる役割です。すると「しっかりメモしてくれてありがとう」とグループ内で評価され、先生にも「協調性がある」と認められるようになりました。
「じゃあ、具体的に何をすればいいの?」という疑問にも塾の先生が答えてくれました。まずは「一言でも発言すること」。最初は「私も〇〇さんの意見に賛成です」という同意からでOK。それだけで「参加意欲がある」と評価されるんです!
うちの子も最初は「〇〇くんの意見に賛成です。理由は…」と付け加えるだけからスタートしました。それが徐々に自信につながり、今では自分から意見を言えるようになりましたよ。
グループワークが苦手でも、小さな一歩から始めることが大切。明日からのグループワークで、ぜひ「一言発言」を意識してみてくださいね!
校則違反・ルール無視が内申点に響く本当の理由
「校則って古いよね~」「ちょっとくらいの違反、大丈夫でしょ?」なんて思ってませんか?実は校則違反が内申点に与える影響は想像以上に大きいんです!塾の先生から「ルールを守る姿勢は社会性の評価につながる」と教えてもらいました。
特に驚いたのは、「校則違反の記録が内申書に残る」ということ。髪型や制服の乱れ、スマホの使用など、日常的な校則違反も「生活態度」の評価として記録されるんですって。
うちの子も中学1年の頃、制服のボタンを外すのが「カッコいい」と思ってやっていたんです。でも塾の先生から「それは校則違反だよ」と指摘され、改めたら担任の先生の態度が変わったんですよ!
★なぜ校則違反が評価に響くのか★ ・規則を守る力は社会人の基本 ・集団生活のルールを理解しているか ・自己管理能力の高さを示す指標
「でも校則って細かすぎ…」という気持ちもわかります。塾の先生が言っていたのは「理由を理解することが大切」ということ。例えば「髪型の規定は清潔感を示すため」「スマホ禁止はトラブル防止のため」など、理由を知ると納得しやすくなります。
うちの子は「なぜそのルールがあるのか」を担任の先生に質問してみました。すると丁寧に説明してくれて、理解を深めることができたんです。その姿勢が「考える力がある」と評価され、内申点アップにつながりました!
「でも、すでに違反してしまった…」という場合は?塾の先生が教えてくれたのは「素直に改める姿勢を見せること」。言い訳をせず、改善する意志を示すことが大切なんだそうです。
うちの子の友達は何度か遅刻を繰り返していましたが、「改善計画書」を自主的に作成して担任に提出したところ、評価が上がったとのこと。過去の違反よりも、これからの姿勢が重要なんですね。
小さなルールを守ることが、内申点アップの第一歩。明日から意識してみませんか?
クラスメイトとのトラブル回避術と対人関係の評価ポイント
「友達関係って内申点に関係ある?」実はかなり関係あるんです!塾の先生から「対人関係は『主体的に学習に取り組む態度』の評価に直結する」と教わって驚きました。
特に先生が見ているのは「問題解決能力」と「協調性」。うちの子は正義感が強く、時々クラスメイトとの摩擦がありました。塾の先生に相談すると「トラブルがあること自体より、どう対処するかが重要」とアドバイスをもらいました。
効果的だったのは「IメッセージとYouメッセージ」の使い分け。相手を責める「Youメッセージ」(あなたが悪い)ではなく、自分の気持ちを伝える「Iメッセージ」(私はこう感じる)を使うことで、対立が減ったんです!
🌟トラブル回避のコツ🌟 ・相手の意見をまず受け止める ・「私は~と感じた」と自分の気持ちを伝える ・解決策を一緒に考える姿勢を見せる
うちの子がグループ活動で意見が合わない子に「君の意見は間違っている」と言ってしまったとき、塾の先生から「それはYouメッセージだね」と指摘されました。代わりに「私はこう考えたんだけど、どう思う?」と言い換えたら、関係がスムーズになったんです。
「でもイライラすることもあるよね…」そんな時は?塾の先生が教えてくれたのは「クールダウンの時間を作る」こと。「少し考える時間が欲しい」と伝えて、冷静になってから対応すると感情的なトラブルを避けられます。
うちの子も数学の問題で意見が合わない時、「ちょっと考える時間をください」と言ってから話し合いを再開したら、先生から「冷静に議論できていますね」と評価されました。
対人関係での評価を上げるには、日頃から「相手の気持ちを考える」習慣が重要。明日からのクラスでの会話で、ぜひ「Iメッセージ」を意識してみてくださいね!
学年別!内申点アップ戦略カレンダー
「内申点対策っていつから始めればいいの?」これ、よく聞かれる質問なんです!答えは「今すぐ」。塾の先生から「中学1年の1学期からが勝負」と言われて驚きました。学年によって内申点の重要性や対策法が違うんです。それぞれの学年に合わせた戦略を立てることが大切ですよ!
中学1年生から始める内申点対策—初年度の重要性
「中学1年生なんてまだ余裕でしょ?」…実はそれ、大きな間違い!塾の先生から「内申点の基礎は中1で決まる」と聞いて驚きました。私も「受験は中3になってから」と思っていたので、目からウロコでした。
なぜ中1が重要かというと、「第一印象の法則」があるから。先生たちの中で形成された初期の評価は、その後も続きやすいんです。うちの子も中1の最初の定期テストで力を入れたら、「頑張る生徒」という評価が定着しました。
中1でやるべきことは「基本的な生活習慣と学習習慣を確立すること」。塾の先生が強調していたのは次の3点です。
💮中1の内申点対策3つのポイント💮 ・提出物を必ず期限内に出す習慣をつける ・テスト前は計画的に勉強する習慣を身につける ・授業中のノートの取り方を工夫する
うちの子は小学校の時から忘れ物が多かったので、「提出物チェック表」を作って冷蔵庫に貼りました。これで忘れ物がなくなり、先生からの第一印象が良くなったんです!
「でもすでに1学期が終わってしまった…」という場合でも大丈夫!塾の先生が言っていたのは「2学期からの変化も評価される」ということ。むしろ「変わった!」と思ってもらえると印象に残りやすいんです。
うちの子の友達は中1の1学期はあまり良くなかったけど、2学期から「提出物ノート」を作って管理したところ、「しっかりしてきたね」と評価が上がったそうです。
今日から始められる簡単なこと、それは「学校からの連絡をメモする習慣」。これだけでも忘れ物が減り、評価アップにつながりますよ!
中学2年生の正念場—内申点が最も変動する時期の乗り越え方
「中2は反抗期で大変…」そんな声をよく聞きますよね。実は内申点においても中2は大きな変動期なんです!塾の先生は「中2こそ内申点の分かれ道」と言っていました。
なぜ中2が重要かというと、学習内容が急に難しくなる時期だから。特に数学や英語は中1との差が大きく、ここでつまずく生徒が多いんです。うちの子も数学で苦戦していました。
塾の先生が教えてくれた中2での対策は「苦手科目を作らないこと」。全ての科目で「4」を目指すより、全ての科目で最低「3」を確保する方が重要なんだそうです。
▲中2で特に注意すべきポイント▲ ・定期テストで「1」「2」を取らない ・部活と勉強のバランスを見直す ・学習計画を自分で立てる習慣をつける
うちの子は部活に熱中するあまり、勉強時間が減って数学が「2」になってしまいました。塾の先生のアドバイスで「部活のある日は電車の中で英単語」「休日の朝は数学」など、スキマ時間を活用する計画を立てたら、内申点が回復!
「でも中2になって急に成績が下がった…」という場合は?塾の先生が教えてくれたのは「早めに先生に相談すること」。「最近勉強のやり方がわからなくなってきました。アドバイスをください」と伝えると、先生も親身になってくれるんです。
うちの子も英語が急に難しくなった時、英語の先生に「どうしたら良いですか?」と相談したところ、ワークの効果的な使い方を教えてもらえました。その後の定期テストで20点アップ!
「中2の正念場」を乗り越えるカギは「自分から助けを求める勇気」。先生や保護者に頼ることも大切な力なんですよ。
中学3年生の内申点逆転プラン—最終局面での効果的アプローチ
「もう中3になっちゃった…手遅れ?」いえいえ、まだ間に合います!塾の先生から「中3でも内申点は上げられる」と教えてもらって、本当に安心しました。
中3の内申点で重要なのは「伸びしろをアピールすること」。完璧である必要はなく、「成長し続けている」ことを示すのが効果的なんです。うちの子も中3の1学期に社会が「2」だったのですが、先生に「どうすれば上がりますか?」と相談したら、最終的には「4」まで上がりました!
📝中3での内申点アップ戦略📝 ・前学年と比べて伸びた点をアピールする ・苦手科目の克服に全力を注ぐ ・三者面談を積極的に活用する
特に効果的だったのは「自己分析シート」の活用。塾の先生に教えてもらったのですが、「前回からどう成長したか」「今後どう改善するか」を書き出して担任に提出するというもの。これが「計画的に学習している」という評価につながりました。
「でも受験勉強で忙しいのに…」そう思いますよね。でも塾の先生が言っていたのは「内申点対策と受験勉強は別物ではない」ということ。例えば、学校のワークを丁寧にやることは、受験対策にもなるんです。
うちの子が実践したのは「学校の提出物を最優先にする」という方法。まず学校の課題をしっかりやってから、受験対策の問題集に取り組むようにしました。これで内申点も上がり、受験勉強も進んだんです!
「でもすでに2学期…」という場合は?塾の先生が教えてくれたのは「最後の逆転チャンス」。3年の2学期末までの内申点が重要なので、今からでも間に合います!特に「提出物の質を上げる」「授業態度を改善する」は即効性があるそうです。
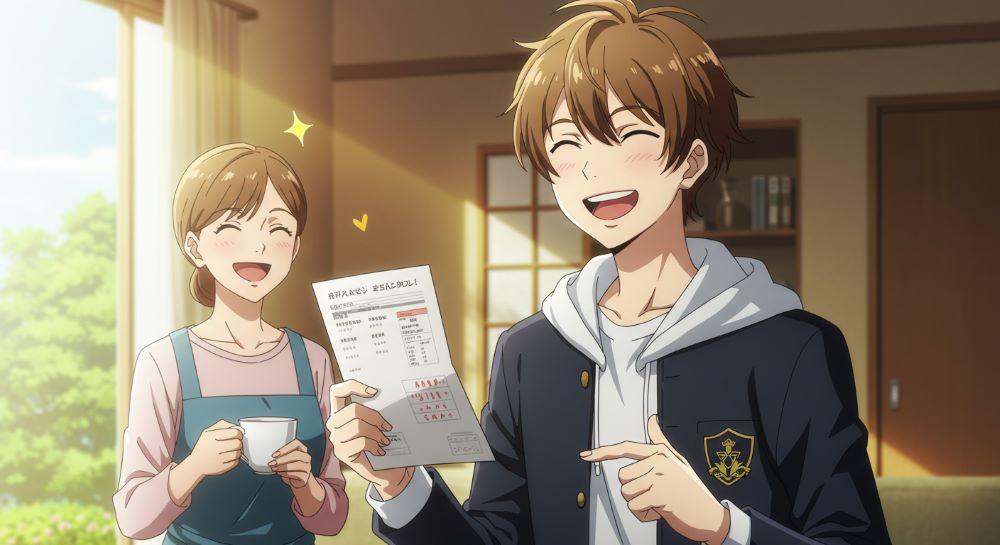
あきらめずに、今日から始めてみませんか?小さな変化が大きな結果につながりますよ!
教科別!内申点アップの秘訣とポイント
「全部の教科で内申点を上げるのは無理…」そう思っていませんか?確かに全教科を完璧にするのは難しいですが、各教科には「評価されるポイント」があるんです!塾の先生に教えてもらった教科別の内申点アップ法を紹介します。科目ごとの特性を理解して、効率的に内申点をアップさせましょう♪
5教科の内申点を上げるための教科別攻略法
「5教科って評価基準が違うの?」実はかなり違うんです!塾の先生から「各教科の先生が見ているポイントを押さえることが大切」と教わりました。うちの子も教科別の対策を始めたら、内申点が上がっていきましたよ。
まず国語!ここでのポイントは「読解力と表現力のアピール」。塾の先生が教えてくれたコツは、「授業中の発言で自分の意見を論理的に述べること」。うちの子は読書感想文を丁寧に書くことを意識したら、国語の内申が「3」から「4」に上がりました!
数学は「解答過程の明示」が鍵。「答えが合っているだけでなく、どう考えたかが重要」と塾の先生。うちの子は解き方を丁寧に書くようにしたら、数学の先生から「考え方がわかりやすい」と評価されました。
▼教科別攻略ポイント▼ ・国語:自分の意見を論理的に述べる、漢字は必ず覚える ・数学:解答過程を丁寧に書く、図を活用する ・英語:発音を意識する、単語テストで高得点を維持 ・理科:実験レポートに考察を充実させる、現象の「なぜ」を考える ・社会:資料を自分で調べる、時事問題に関心を持つ
特に効果的だったのは英語での「音読ノート」の活用。塾の先生のアドバイスで、教科書の音読回数を記録するノートを作ったら、英語の先生に「家でもよく練習していますね」と評価されました。
「でも全教科対策するの大変…」という場合は?塾の先生が教えてくれたのは「弱点強化」の考え方。例えば「4」と「2」の教科があれば、「2」を「3」にする方が効果的なんです。うちの子も社会が「2」だったので、集中的に対策したら「3」になり、内申点の合計が大幅アップしました!
教科別の対策を始めるなら、まずは「2」の教科を「3」にすることから。小さな一歩が大きな変化につながりますよ!
実技4教科で高評価を得る具体的な行動パターン
「実技教科なんて適当でいいじゃない?」…実はそれ、大きな間違い!塾の先生に「実技4教科は内申点アップの穴場」と教えてもらって驚きました。音楽、美術、保健体育、技術・家庭科の4教科は意外と内申点が取りやすいんです!
なぜ実技教科が重要かというと、「主要5教科で内申が取りにくい生徒でも、ここで挽回できる」から。うちの子も数学や理科は苦手でしたが、実技教科で「5」を取れたおかげで内申点の合計が大幅アップしました。
塾の先生が教えてくれた実技教科での評価ポイントは「積極性」と「準備の良さ」。特に体育は「運動神経」より「取り組む姿勢」が重視されるんだそうです。
🎵実技教科で評価アップのコツ🎵 ・音楽:小テストをしっかり対策、歌うときの姿勢を良くする ・美術:アイデアスケッチを丁寧に、作品の意図を明確に ・体育:準備運動を真剣に取り組む、チームプレーを意識する ・技術・家庭:安全家庭:安全面に配慮する、道具の後片付けをきちんとする
実はうちの子、音楽が苦手で内申が低かったんです。でも「歌う姿勢」だけ意識させたら、先生に「声が出るようになった」って褒められて評価が上がったんですよ!体育も「速く走れなくても、準備運動をきちんとやって、応援をしっかりする」ことを意識させたら、内申が上がりました。
それから見落としがちなのが授業の準備物!特に実技教科は「忘れ物」が減点ポイントになりやすいので、前日の夜に「明日の実技教科の準備物チェック」をするクセをつけるといいですよ。うちでは「実技教科準備カレンダー」を作って、「明日は技術の時間、定規と鉛筆セット必要だよ」って確認するようにしています。
あと、担任の先生が総合的な学習の時間の担当じゃない場合は、その教科の先生との接点が少なくなりがちなんです。だから「総合」の授業での発言や提出物の質にも気を配るといいですよ。うちの子は「総合」のテーマ学習でちょっと頑張ったら、担当の先生から担任に良い評価が伝わって、内申全体の印象が良くなったみたいです。
最後に、実技教科で作った作品やレポートは家でも大切に扱うようにして、「学校での学びを大切にしている」という姿勢を見せるのも効果的ですよ!うちでは美術の作品を玄関に飾っておいたら、子どもが「次はもっと上手に描きたい」ってやる気を見せてくれました。こういう小さな積み重ねが、結果的に内申アップにつながるんですよね♪
みなさんも、ぜひ試してみてくださいね!
まとめ:内申点アップは日々の積み重ねが鍵—今日からできる具体的行動計画
結局のところ、内申点アップの”裏ワザ”って、毎日の小さな積み重ねなんです!具体的には①授業の準備をしっかりする②提出物は期限を守る③発言を少しずつ増やす④部活や委員会活動に前向きに取り組む⑤定期テスト2週間前から計画的に勉強する…これだけでも全然違います!まずは今日から「提出物チェックリスト」を冷蔵庫に貼るところから始めてみませんか?小さな成功体験が子どもの自信につながって、内申アップの好循環が生まれますよ!
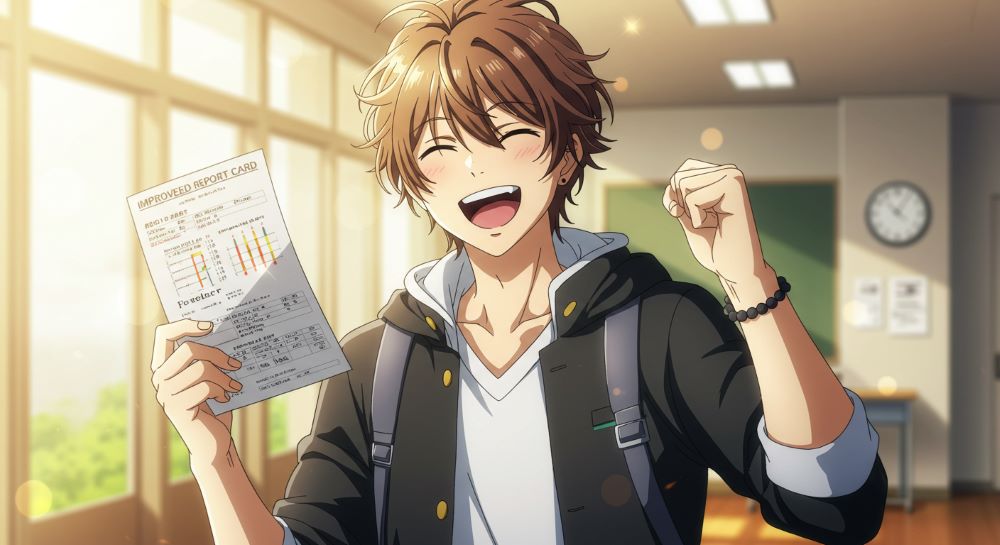
コメント