こんにちは!
受験生のお子さんを持つ皆さん、「内申点」という言葉にイラッとしたことありませんか?
うちの息子も「内申点ってバカバカしい!」と叫んだ日から、我が家の受験対策が本格的に始まりました。
今日はそんな内申点との向き合い方や、内申が気になる場合の高校選びについてお話しします!
中学生が「内申点ってマジでバカバカしい」と感じる5つの理由
中学生になると急に耳にするようになる「内申点」。テストでいい点を取っても、なぜか内申は上がらない…そんな疑問や不満を感じていませんか?
頑張ったテストの点数が全く内申に反映されない現実
テストで90点取ったのに「3」だったり、80点なのに「5」だったり…なんでこんなことになるの!?って思いますよね。実は内申点って、単純にテストの点数だけじゃないんです。
うちの息子は数学のテストで85点取ったのに内申は「3」。隣のクラスの子は78点で「4」だったって知った時は、もう家中が大騒ぎでした(笑)。
なぜこんな差が?調べてみると、「定期テスト」だけでなく、「小テスト」や「提出物」、さらには「授業態度」までもが評価対象になっていたんです!
【評価の謎】これって地域や学校によっても基準が違うから余計にわかりにくい。息子が「これじゃテスト勉強する意味ないじゃん!」と怒るのも無理ないかも…。でも実はここに対策のヒントがあったんです。
「挙手」や「提出物」が内申を左右する理不尽さ
「授業中に手を挙げる」「提出物を期限内に出す」—こんな当たり前のことが内申点に大きく影響するって知ってました?これを知った時の衝撃ったらなかったです!
息子は算数は得意でしたが、人前で発言するのが苦手。テストはいつも80点以上なのに、授業中は黙々と問題を解くタイプ。ある日担任から「テストの点はいいけど、もっと授業で発言しないと内申は上がらないよ」と言われたんです。
【参加度重視】これって内向的な子にとっては地獄のシステム…。特に思春期の中学生が無理して手を挙げるって、どれだけハードルが高いか。先生方にはもっと理解してほしいですよね。うちの息子は「わかっているけど発言できない」という葛藤で悩みました。皆さんのお子さんも同じような経験ないですか?
提出物も「ただ出す」んじゃなく「丁寧に仕上げる」ことが求められる。忙しい部活との両立で精一杯なのに、さらに「見栄え」まで気にしないといけないなんて…。子どもたちの負担は相当なものです。
学校の授業だけでは不安…という方に。
我が家は通信教育で『提出物の質』を劇的に改善しました。
特に理科や社会のレポート課題は、通信教育の教材を参考にするだけで見違えるほどレベルアップ!
内申対策に特化したコースもあるので、チェックしてみてください。
教師の主観で決まる評価基準に怒りが爆発
これが一番モヤモヤするポイント!同じ答案でも、教師によって評価が全然違うことがあるんです。厳しい先生と緩い先生の差が激しすぎて…💢
息子の国語の先生は超厳格派。小論文の採点では「自分の意見が明確に書かれていない」と減点されまくる一方、他のクラスでは「自由な発想でよく書けている」と高評価される同じような答案…。「え?これってどっちが正解なの?」って混乱しますよね。
【先生バイアス】実はこの「先生の好み」による評価のブレが内申の最大の問題点。客観的な基準がなく、担当教師の主観に左右されるシステムって本当に公平と言えるのでしょうか?特に表現力を評価する国語や社会などは、教師の価値観によって大きく点数が変わります。お子さんが「なんで?」と感じるのは当然の疑問です。こういう不透明さが「内申点バカバカしい!」という叫びにつながるんですよね。
内申対策に悩んでいた我が家が、最終的に頼ったのがオンライン個別指導でした。
学校の先生には相談しにくい『内申の上げ方』を、プロの塾講師が具体的にアドバイスしてくれたんです。
特に提出物の質の上げ方や、授業態度の見せ方まで教えてもらえて、息子の内申は3ヶ月で3ポイントアップ!
無料体験だけでも受ける価値ありますよ。
でも意外にね、先生がつける評定は見られてるなぁ~って感じることがあります。
もし、評定に「2」がついている人は、こちらを参考にまずは生活態度から見直すことが重要ですよ!
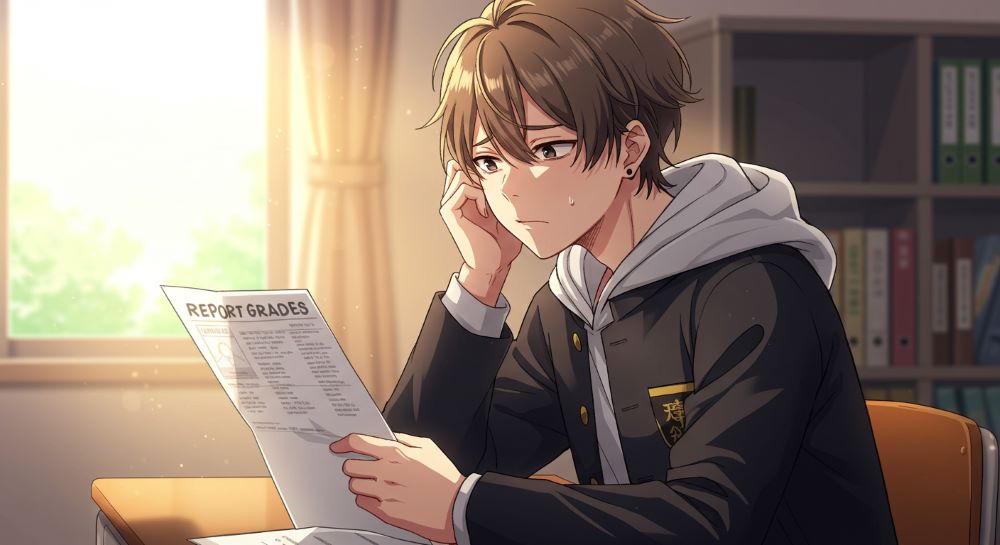
学校によって内申の付け方が違いすぎる不公平感
友達との会話で発覚する内申の謎。「うちの学校は5段階評価」「うちは10段階」「内申点の計算方法が全然違う!」—こんな会話、聞いたことありませんか?
近所の中学3校を比べただけでも、評価基準がバラバラで驚きました。Aの学校は「授業態度重視」、Bの学校は「定期テスト80%・提出物20%」、Cの学校は「毎回の小テストが命」など。同じ市内なのに全然違うシステム!
【学校格差】これって受験では大きな差になります。特に「内申が甘い学校」と「厳しい学校」があるのは事実。同じ実力なのに通っている学校によって内申点に差がつくなんて、本当に公平な評価といえるのでしょうか?ある地域では隣接する中学校同士で「平均内申点」に2ポイント近い差があったという話も…。子どもたちが不公平感を感じるのも無理はないですよね。
公立高校と私立高校で求められる内申の謎
公立と私立で内申の重要度が全然違うって知ってました?うちは最初これを知らなくて、かなり遠回りしちゃいました…。
公立高校は「内申点+当日の試験」で合否が決まりますが、私立高校は学校によって「内申ほぼ無視」というところもあります。特に難関私立は「当日の試験だけ」という学校も多いんです。
でも油断は禁物!多くの私立でも「同点なら内申で判断」というルールはあります。また、推薦入試なら内申が超重要になるケースも。自分の志望校が「内申をどれだけ重視するか」を早めにリサーチしておくことが大切です。
子どもの将来がこんな不透明なシステムで左右されると思うと、親としてはやりきれない気持ちになりますよね。でも、このシステムを理解して賢く対応することも大切です。
それでも公立高校を選ぶ場合は内申重要になってくるのが現実。愚痴を言ってても仕方がありません。
今からでも遅くない!
息子も内申も上がった塾の先生から教えてもらった秘密の作戦を紹介しるので、みんな頑張って!
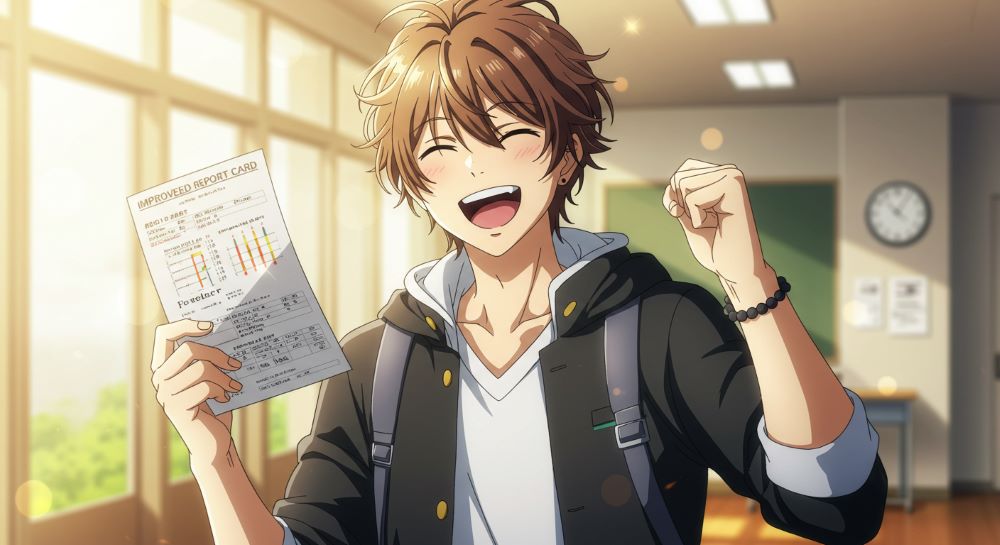
内申点がバカバカしいと思った場合の高校選び
内申に不満があっても、高校受験は避けて通れません。では、内申点に悩む子どもにはどんな高校選びがベストなのでしょうか?
内申より当日点重視の高校を狙え!私立高校の選び方
内申点に不満がある場合、「当日点重視型」の高校を選ぶのが賢明です!特に私立高校には「内申ほぼ無視」の学校がたくさんあります。
うちの息子の場合、内申は平均的でしたが、テストの点数は良かったため、「当日の試験で9割以上を占める」私立高校をメインに受験しました。特に難関私立や、独自の校風を持つ私立高校は「学校の雰囲気に合う生徒」を重視する傾向があり、内申よりも当日の試験や面接での印象を重視してくれます。
【私立攻略】私立高校のパンフレットやホームページには記載されていないことも多いので、学校説明会で直接「内申と当日点の比率はどのくらいですか?」と質問するのがおすすめ。中には「内申は参考程度」と教えてくれる学校もあります。オープンスクールでは在校生に「内申どれくらいだった?」と聞くのも有効です。彼らの生の声から「実際の内申ボーダー」がわかることも!
私立高校は学費は高めですが、「子どもの実力を正当に評価してくれる」という点では安心感がありました。
実技試験のある高校なら特技を活かせる!特色入試の活用法
内申点が低くても、特技や個性で勝負できる高校もあるんです!「実技試験」「特色入試」を活用しましょう。
例えば、芸術系高校(美術・音楽・演劇など)、スポーツ推薦がある高校、国際科や理数科など専門性の高い学科は、「特定分野の才能」を重視する傾向があります。うちの息子の友人は内申が低めでしたが、サッカーの実技試験で高評価を得て体育科のある高校に合格しました。
【特技活用】特に「実技試験の配点が高い」学校を探すのがポイント。実技や小論文で5割以上を占める入試なら、内申が多少低くても挽回できる可能性が高いです。また、「総合問題型」の入試を採用している学校も、暗記よりも思考力や表現力を評価してくれるので、テストは得意だけど内申が低い子には向いています。
お子さんの得意分野や興味を活かせる高校を探せば、内申に縛られずに可能性を広げられますよ。高校は「行きたい学校」より「行ける学校」と妥協するのではなく、子どもの個性が活きる場所を見つけてあげたいですね。
通信制・サポート校という選択肢も視野に入れよう
極端な話ですが、内申点に本当に悩んでいるなら、「内申不要」の高校という選択肢もあります。通信制高校やサポート校は、多くの場合「書類選考+面接」のみで入学できます。
最近の通信制高校は昔のイメージと違って、充実した学習環境や特色ある専門コースを備えた学校が増えています。特に「サポート校」と呼ばれる通信制高校のサポート施設は、毎日通学して友達と一緒に学べる環境があり、部活動や学校行事も充実しています。
【新時代の選択肢】通信制やサポート校に通いながら、得意科目を伸ばして大学受験を目指す生徒も増えています。「高校受験のために無理に内申を上げる」より、「自分の学びたいことに集中できる環境」を選ぶという発想の転換も必要かもしれません。実際、私の知人の子どもは通信制高校から難関大学に進学しました。「受験のための内申」から解放されて、むしろ伸び伸びと実力を伸ばせたようです。
特に「学校の評価と実力が合っていない」と感じるお子さんには、柔軟な選択肢として考慮する価値があります。子どもの個性や学習スタイルに合った環境を選ぶことが、長い目で見た「学力」や「自己肯定感」につながるのではないでしょうか。
内申廃止への動き
実は「内申点はバカバカしい」という意見は、私たち親子だけのものではないんです。教育界でも内申点の問題点が指摘されています。
教育改革で変わりつつある内申点の位置づけ
最近の教育改革の流れでは、「内申点偏重」から少しずつ方向転換が始まっています。
文部科学省も「多面的・総合的な評価」を推進し、単なる点数や内申だけでなく、「思考力」「判断力」「表現力」などを重視する流れに。実際、いくつかの地域では内申点の比率を下げたり、「絶対評価」に切り替えたりする動きが出てきています。
【改革の波】こうした動きの背景には「AIやグローバル時代に必要な力は内申では測れない」という認識があります。特に「新学習指導要領」では、「主体的・対話的で深い学び」を重視し、従来の「知識詰め込み型」から脱却する方針。これに伴い、高校入試でも「内申+ペーパーテスト」という従来の形式から、「思考力を測る問題」「探究活動の評価」などを取り入れる動きが広がっています。
教育委員会のホームページや入試説明会で「入試改革」の情報をチェックしておくと、最新の動向がわかりますよ。地域によっては「内申点の計算方法変更」や「当日点の比率アップ」といった変化が起きているかもしれません。
先進的な学校で始まっている「ポートフォリオ評価」とは
一部の先進的な学校では、内申点に代わる新しい評価方法として「ポートフォリオ評価」を取り入れ始めています。
「ポートフォリオ評価」とは、テストの点数だけでなく、「生徒の成長の記録」を多面的に評価する方法。例えば「プロジェクト学習の成果物」「探究活動の記録」「課外活動での成果」などを蓄積し、それを総合的に評価します。
【未来型評価】この評価方法のメリットは「子どもの個性や強みを活かせる」こと。テストが苦手でも、探究活動やプレゼンが得意な子は、その力を評価してもらえます。また、「先生の主観に左右されにくい」という利点も。複数の教師や時には外部の専門家も交えて評価するため、より公平な判断が期待できます。
特にIB(国際バカロレア)認定校や、SGH(スーパーグローバルハイスクール)、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)などの先進的な高校では、すでにこうした評価方法が取り入れられています。「内申点よりも実際の力を見てほしい」というお子さんには、こうした学校も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
内申点に頼らない「未来の入試」はどうなる?
教育関係者の間では「内申点に代わる評価方法」についての議論が活発化しています。未来の入試はどうなるのでしょうか?
一部の教育専門家は「内申点を廃止して、当日の試験と面接・作品評価の組み合わせにすべき」と主張しています。また、「思考力・判断力・表現力を測る記述式問題の充実」「小論文や課題研究の重視」など、より実践的な力を評価する方向への転換も検討されています。
【未来の入試】特に注目されているのが「CBT(Computer Based Testing)」を活用した新しい入試形式。PCやタブレットを使った問題解決型の試験で、単なる暗記ではなく「情報の活用力」や「考える力」を測ります。また、「複数回受験可能な入試」や「長期的な課題に取り組む入試」など、一発勝負ではなく継続的な成長を評価する仕組みも検討されています。
こうした変化は一朝一夕には実現しませんが、少しずつ「内申点バカバカしい!」という声に応える形で、入試制度は変わりつつあります。お子さんの世代、そしてこれからの子どもたちには、もっと公平で多様な評価方法が整備されることを期待したいですね。
「内申点はバカバカしい」と思いながらも高校合格までたどり着いた軌跡
愚痴だけでは何も変わりません。内申に不満を感じながらも、最終的に志望校に合格するためにやったことをシェアします!
3年間の内申積み上げ戦略で志望校に逆転合格した秘訣
大事なのは「早め早めの対策」です。内申は3年間の積み重ねなので、中1から意識することが重要でした。
1年生は「提出物を完璧に」「授業態度を良くする」ことに集中。2年生からは「定期テスト対策」を強化しつつ、「発言」や「質問」を増やして積極性をアピール。3年生では「総合的な学習の時間」や「委員会活動」にも力を入れました。
こうした3年間の積み重ねが功を奏し、最終的には「9科で36」という内申を取ることができました。当日の試験も頑張り、第一志望に合格できたときは本当に感動しました。
内申対策に悩んでいた我が家が、最終的に頼ったのがオンライン個別指導でした。
学校の先生には相談しにくい『内申の上げ方』を、プロの塾講師が具体的にアドバイスしてくれたんです。
特に提出物の質の上げ方や、授業態度の見せ方まで教えてもらえて、息子の内申は3ヶ月で3ポイントアップ!
無料体験だけでも受ける価値ありますよ。
塾の先生から教えてもらった秘密の作戦を実行したら、内申が上がったんです!みなさんもぜひやってみてね。
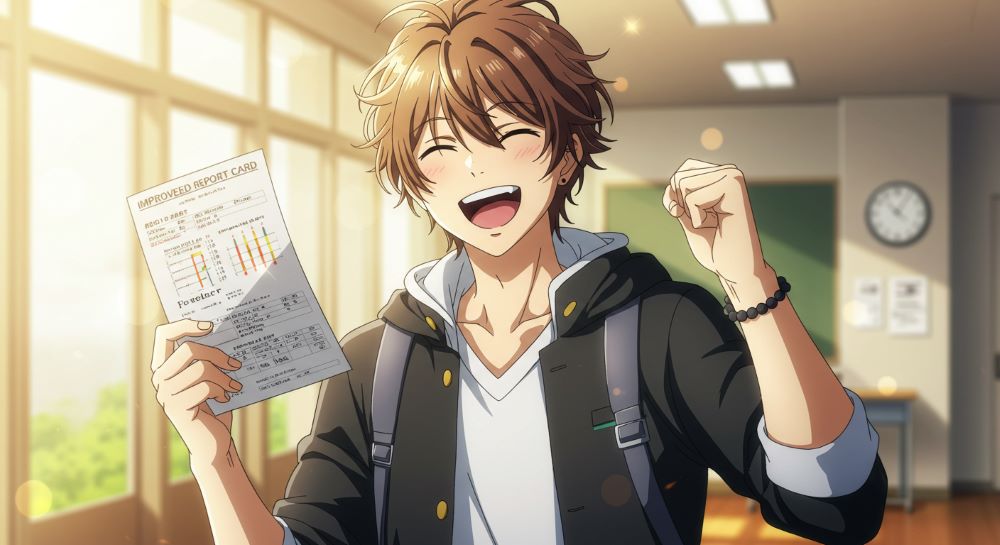
内申よりも当日点で勝負する「捨て内申作戦」の真実
ちょっと過激なタイトルですが、実は「内申に執着しすぎない」という選択肢もあります。特に私立志望の場合、「当日の点数勝負」に集中する戦略も有効です。
うちの場合、公立と私立の併願でしたが、第一志望の私立は「内申より当日点重視」の学校。そこで「内申は最低限維持しつつ、当日の試験対策に時間を使う」という方針に切り替えました。
【戦略転換】具体的には、「内申を上げるための小テスト対策」より「入試問題の演習」に時間を使いました。内申対策に使う時間を、志望校の過去問演習や弱点補強に充てたんです。内申に過度にこだわるのではなく、「合格するために何が必要か」を冷静に分析することが大切だと感じました。
結果、内申は「そこそこ」でしたが、当日の試験で高得点を取り、志望校に合格できました。もちろん「内申を捨てる」わけではなく、「エネルギー配分を考える」という意味です。志望校研究をしっかりして、どこに力を入れるべきか見極めることが大切だと実感しました。
学校の先生も教えない内申点の本当の重要度と見極め方
学校では「内申が全て」のように言われがちですが、実は入試の仕組みはもっと複雑。この「本当の重要度」を知ることが大切です。
公立高校の場合、多くは「内申点×α+当日点」という形で合否を決めます。この「α」(内申の倍率)がどれくらいかで戦略が変わってきます。地域によって「内申3倍」「内申1倍」など大きく異なるので、まずは自分の地域の計算式を確認しましょう!
【情報収集】地域の入試説明会や過去の合格者データを分析すると、「実際にどれくらいの内申と当日点の組み合わせで合格できるか」が見えてきます。うちは先輩保護者から情報収集して「内申30以上あれば当日6割で合格圏内」という目安を立てました。
また、志望校ごとの「足切り内申」(最低限必要な内申点)を調べておくのも重要です。「この学校を受けるなら内申最低何点必要」という情報は、進路指導の先生や塾の先生に相談すると教えてもらえることが多いですよ。
それに最後の最後に内申が上がるどんでん返しもあるのを知っていましたか?まだまだ希望は捨てないで!
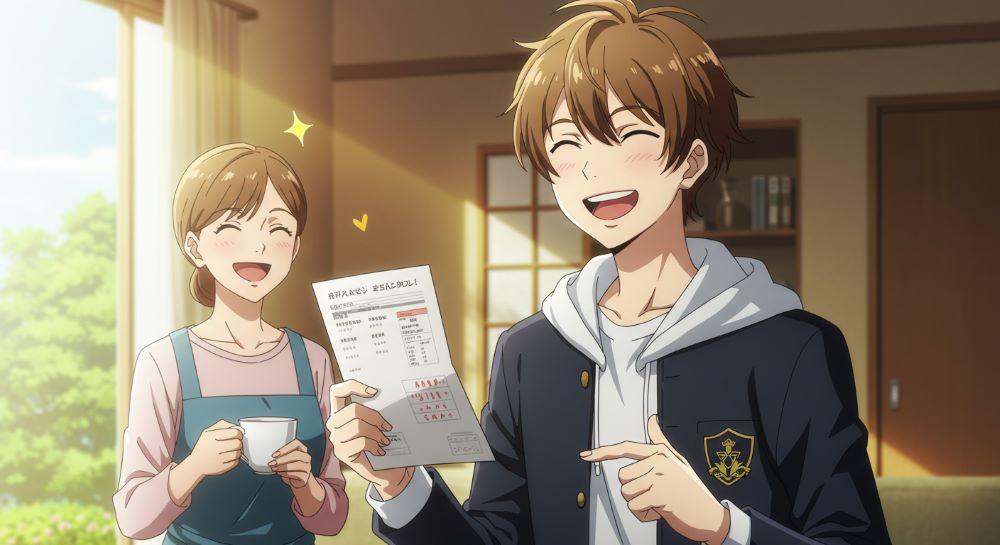
親として知っておくべき「内申点はバカバカしい」と言う子どもへの対応術
内申に悩む子どもに、親としてどう寄り添えばいいのでしょうか?
内申点の不満をバネに変える親子コミュニケーション術
「内申点バカバカしい!」という子どもの叫びは、実は成長のチャンスです。まずは「否定せずに共感する」ことから始めましょう。
「それ、わかるよ。不公平に感じるよね」と共感した上で、「じゃあ、どうする?」と一緒に考えるスタンスが大切です。苦情を言うだけでなく「解決策を考える力」を育てる機会になります。
【心の支え】うちでは「内申点は完璧じゃないシステムだけど、今はそれが入試のルール。ルールの中で最大限自分を活かす方法を考えよう」と話しました。「理不尽なルールにも適応する力」は社会に出てからも役立つスキルだと伝えると、息子も少しずつ前向きになっていきました。
また、「内申だけが全てじゃない」と視野を広げることも大切。「内申が良くても幸せとは限らないし、内申が悪くても素晴らしい高校生活や将来は実現できる」という価値観を伝えることで、子どもの心の余裕が生まれます。
「学校の評価」と「本当の実力」のギャップを埋める家庭学習法
内申点と実力にギャップを感じる子どもには、「本当の学力をつける」ことに集中させましょう。
学校のテストや課題とは別に、「実力を客観的に測る機会」を設けることが有効です。例えば、「模試」や「検定試験」などの外部評価を活用する、オンライン学習サービスで自分のペースで学ぶなど、学校の評価に縛られない学習の場を作りましょう。
内申に自信が持てないなら、客観的な実力を証明できる『検定』がおすすめ!英検や数検は高校入試でも加点対象になることが多く、何より『自分は学校の評価以上の実力がある』という自信につながります。オンラインで対策できるサービスもあるので、気軽に挑戦できますよ。
【実力重視】息子の場合は「英検」「数検」などの検定試験にチャレンジすることで、「学校の評価より自分は実力がある」という自信を取り戻しました。また、オンライン学習サイトで難関校レベルの問題に取り組むことで、「学校の授業より先に進んでいる」という実感も得られたようです。
こうした「学校外での成功体験」が、「内申が全てじゃない」という感覚を育てます。特に内申に悩むお子さんには、学校以外の場で「自分は頑張れる」「認められる」という体験が何より大切です。
内申点に振り回されず自信を持たせるメンタルサポート術
最後に大切なのは、「内申点と自己価値は別」だということを伝えること。子どもの内面の成長を認め、自信を育てましょう。
日々の会話で「テストの点数や内申以外の良いところ」を具体的に言葉にして伝えることが効果的です。「優しさ」「粘り強さ」「創造性」など、内申には反映されない価値を認める言葉かけを意識しました。
【自信育成】また、「失敗しても大丈夫」というメッセージも重要。「内申が下がっても人生は終わらない」「別の道もある」と伝えることで、子どもは「全てを失う恐怖」から解放されます。うちでは「どんな結果になっても、次の作戦を一緒に考えよう」と約束していました。
そして何より「親の愛情は内申と関係ない」ことを態度で示すことが大切。ついつい「内申のために」と口うるさくなりがちですが、「あなたを信じている」「応援している」というメッセージを繰り返し伝えることで、子どものメンタルは守られます。
内申に悩む時期は長くありません。この時期を親子で乗り越えれば、きっと素敵な高校生活が待っています。「バカバカしい」と思えるシステムにも、うまく対応する力を身につけて、志望校合格を目指しましょう!
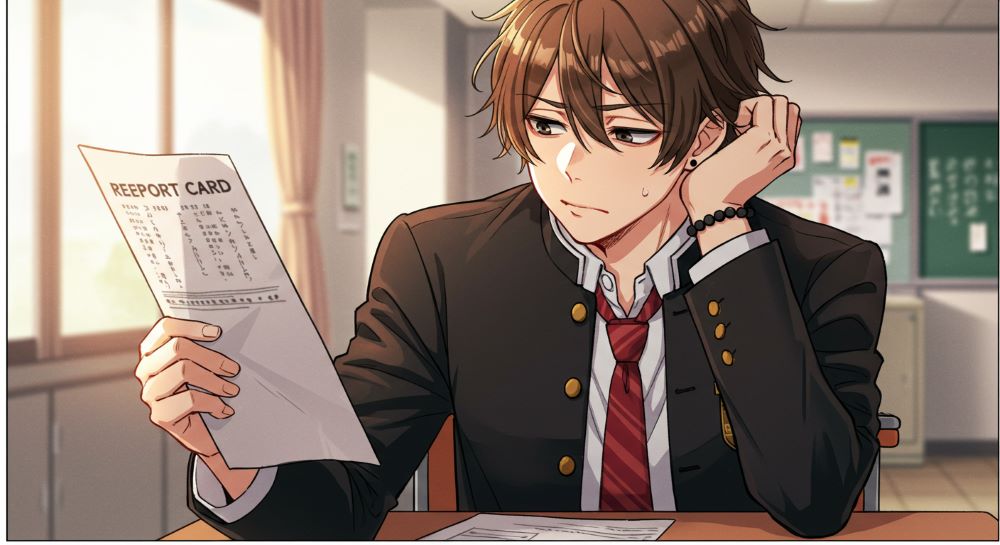
コメント