こんにちは!中学生のお子さんの成績で「2」がついて心配されているパパママも多いのではないでしょうか?私も中学生の母親として、成績表を見るときはドキドキします(^^;)
今回は「なぜ成績に2がつくのか」についてお話しします。一緒に原因を理解して、どうすれば改善できるか考えていきましょう!
中学校の成績で2という評価がつく決定的な理由
まず知っておきたいのは、成績の「2」は偶然つくものではなく、いくつかの明確な理由があるということ。ここをしっかり理解することが最初の一歩です!
授業中の態度が悪く「学習妨害」と判断される生徒の特徴
中学校の先生たちが「この子には2をつけざるを得ない」と判断する大きな理由の一つが、授業中の態度です。
具体的にどんな行動が問題視されるかというと… ・スマホをこっそり見る ・友達とのおしゃべりが止まらない ・教科書やノートを忘れる ・指示を聞いていない
こういった行動は、先生から見ると「学習妨害」と判断されることも。東京都内のある中学校では、授業態度だけで評価の30%が決まるというデータもあります。
でも、ちょっと待って!お子さんは「わからないから」退屈になって違うことをしているかもしれません。学習内容についていけないことが原因なら、まずはそこをサポートしてあげることが大切ですよね。
「なんで授業中におしゃべりするの?」と責めるより、「今日の授業で難しかったところある?」と聞いてみると、思わぬ発見があるかもしれませんよ♪
やる気スイッチが入らない「無気力状態」の見分け方
「最近うちの子、やる気がなくて…」というお悩み、よく聞きます。実は、この「無気力」が評定2の大きな原因になっていることが多いんです。
無気力な状態の中学生によく見られるサイン:
❤ 宿題をギリギリまでやらない ❤ 授業中にあくびが止まらない ❤ 「別にいいや」が口癖になっている ❤ テスト前なのに勉強しない
特に気をつけたいのは、この状態が長く続くと「学習性無力感」という状態になることです。「どうせやっても無駄」という思考パターンに陥り、さらに成績が下がる悪循環に…。
でも大丈夫!中学生の脳は可能性に満ちています。小さな成功体験を積み重ねることで、驚くほど変わることも珍しくありません。
うちの子も一時期「勉強なんて意味ない」と言っていましたが、得意な理科から少しずつ取り組ませたら、他の教科にも興味が広がっていきましたよ。あなたのお子さんの「得意」は何でしょうか?そこから始めてみませんか?
テスト点数が基準値を大きく下回り挽回が難しいケース
中学校の評価で一番わかりやすいのは、やはりテストの点数ですよね。多くの学校では、
テスト30点以下→ほぼ確実に評定2
テスト40点前後→境界線
テスト50点以上→評定3の可能性大
という目安があります。特に数学や英語は積み重ねが重要な教科なので、一度理解できないところがあると、そこから一気に点数が下がってしまうことも。
千葉県のある中学では、定期テストの平均点が35点以下の場合、補習に参加することが義務付けられているそうです。評定2をつける前に、学校側も対策を講じているんですね。
あれ?お子さんのノートを見たことありますか?実は、テストの点数が悪い子のノートには特徴があるんです。板書が途中で終わっていたり、問題の解き方が書かれていなかったり…。まずはノートチェックから始めてみるのも一つの方法かもしれませんね!
提出物の未提出や期限遅れが続く習慣化した問題
「宿題やった?」って毎日聞いてるのに、なぜか提出してない…そんな経験ありませんか?
実は、中学校では提出物の管理がしっかりされていて、未提出や遅れが続くと評価に大きく影響します。特に「技術・家庭科」や「美術」などの実技教科では、作品の提出が評価の8割を占めることも!
よくある提出忘れパターン: 🌟 完成したけど提出し忘れ 🌟 途中まで作ったけど仕上げていない 🌟 そもそも取り組んでいない 🌟 提出期限を覚えていない
神奈川県の調査では、評定2がついた生徒の約65%が提出物の未提出を理由としていたそうです。意外と見落としがちなポイントかもしれませんね。
「宿題終わった?」と聞くより、「今日の宿題、一緒に確認してみようか?」と声をかけてみるのはどうでしょう。一緒に確認することで、お子さんも提出物の管理方法を学べますよ。
評定2がもたらす現実的な影響と高校受験への打撃
成績表に「2」があると、どんな影響があるのか知っておきたいですよね。正しく理解して、適切に対応していきましょう!
全生徒の約14%が該当する「評定2」の実態調査
実は、中学生全体で見ると「評定2」がつく生徒は約14%程度なんです。決して珍しいことではありません。
でも、この14%という数字、教科によって大きく違うんですよ。
例えば: ・数学:約20%(最も評定2が多い) ・英語:約17% ・国語:約12% ・体育:約5%(最も評定2が少ない)
文部科学省の調査によると、数学では5人に1人が評定2という結果も。特に「関数」や「図形の証明」につまずく生徒が多いようです。
「うちだけじゃないんだ」と少し安心した方もいるかもしれませんね。でも、高校受験を控えた中学3年生なら、この評定2を何とかしたいところ。あなたのお子さんはどの教科が苦手ですか?まずはその教科に集中して取り組むのがおすすめです♪
たった1つの「2」で狭まる公立高校の選択肢と対策法
「一つくらい2があっても大丈夫でしょ?」
…実はそうとも言えないんです。多くの公立高校では「内申点」という形で中学の成績が評価され、たった1つの「2」でも合格可能性が大きく下がることがあります。
特に人気校や進学校では、内申点の「足切り」があることも。
例えば、東京都の場合:
・偏差値65以上の高校:1教科でも「2」があると厳しい ・偏差値60前後の高校:2教科以上「2」があると厳しい ・偏差値55以下の高校:3教科以上「2」があっても可能性あり
「じゃあどうすればいいの?」って思いますよね。まずは志望校の過去の内申点ボーダーを調べてみましょう。それを目標に、特に「2」がついている教科の改善を目指すのが効果的です。
それと、公立高校の場合、中3の成績が特に重視されることが多いので、今が中1・中2なら、まだまだ十分挽回できますよ!
どうしても、評定2から上がらないって人は、他の選択肢を考えつつもあきらめないで頑張って下さいね。
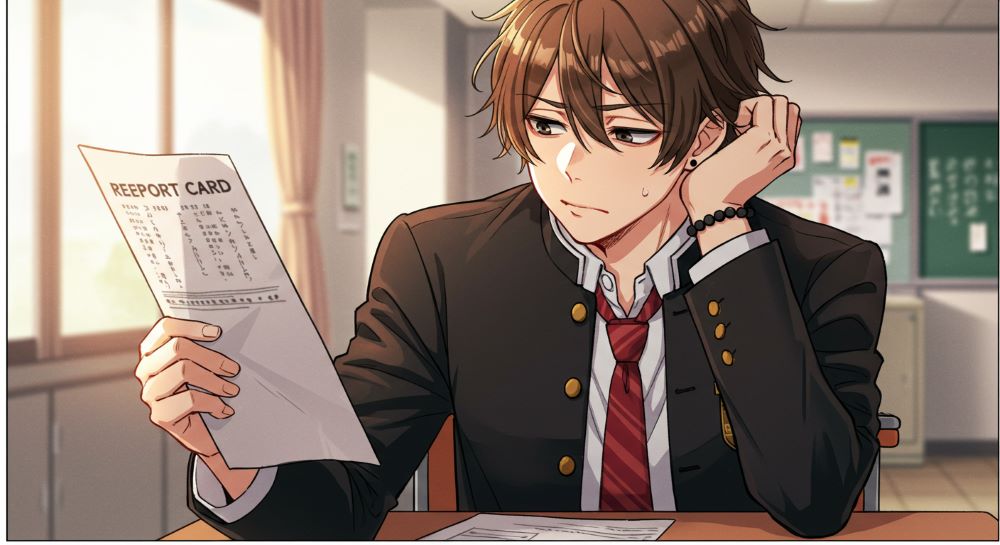
成績2からの脱出戦略!親子でできる即効性のある改善方法
では具体的に、どうすれば評定2から脱出できるのか、実践的な方法を見ていきましょう!
まずはオール3を目指す!生活習慣から見直す基本ステップ
成績アップを目指すとき、つい勉強法ばかりに目が行きがちですが、実は「生活習慣」の見直しがとても大切なんです。
中学生の時期は心身の成長が著しく、睡眠や食事が学習効率に直結します。特に夜10時〜深夜2時の睡眠は、記憶の定着に重要と言われています。
改善したい生活習慣チェックリスト: ⭐ 毎日同じ時間に起きる ⭐ スマホは勉強中はカバンにしまう ⭐ 夕食後に30分でも勉強時間を作る ⭐ 朝食はしっかり食べる
文部科学省の調査でも、規則正しい生活習慣を持つ中学生は、そうでない生徒に比べて平均で1.2ポイント成績が高いというデータがあります。
「うちの子、夜更かししすぎ…」なんて悩んでいませんか?いきなり厳しく制限するより、「明日早く起きたいから、今日は少し早く寝てみない?」と提案してみるのがおすすめです。小さな成功体験から始めていきましょう!
オール3まで頑張れたら、あとはどんどん評定UPを狙っていきましょう!
ここからはコチラの秘策を実践してみてくださいね。(#^.^#)
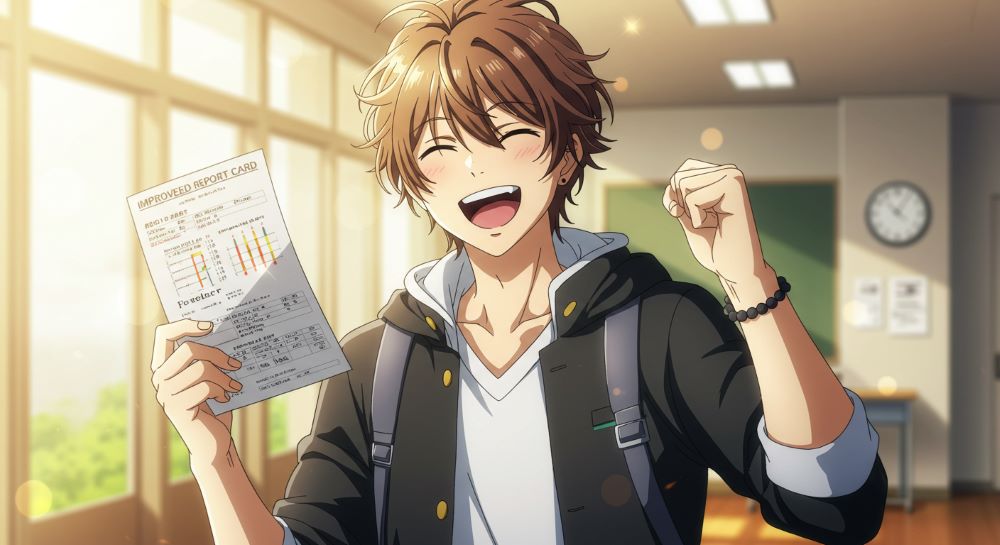
教科別・評定2から抜け出すための効果的な学習法
教科によって、効果的な学習法は異なります。「闇雲に勉強しても成績が上がらない…」というお子さんには、教科別のアプローチがおすすめです。
【数学が苦手な場合】 数学は積み重ねの教科。つまずいている単元を特定することが最重要です。例えば「方程式」でつまずいているなら、その前の「正負の数」に戻って復習するのが効果的。最近では、YouTubeでわかりやすく解説している無料チャンネルもたくさんありますよ。
【英語が苦手な場合】 英語は「音」からのアプローチが効果的です。単語を書いて覚えるより、声に出して読む方が記憶に残りやすいんです。中学英語の基本文は400程度と言われていますから、それを声に出して練習するだけでもグッと成績アップにつながります。
お子さんにとって学びやすい方法は人それぞれ。「目で見て覚える子」「耳で聞いて覚える子」「体を動かして覚える子」…あなたのお子さんはどのタイプでしょうか?その特性に合わせた学習法を試してみてくださいね。
最後に、大切なのは「少しでもできた!」という成功体験です。難しい問題より、確実に解ける問題から取り組み、少しずつレベルアップしていく方法が、モチベーション維持につながりますよ♪
まとめ:中学校で成績に2がつく原因と対策の総括ガイド
いかがでしたか?「中学校で成績に2がつく理由」について、原因と対策をお話ししてきました。
最後に大切なことをお伝えします。成績は確かに大切ですが、それ以上に大切なのは「学ぶ意欲」です。評定が「2」から「3」になっても、学ぶ楽しさを見つけられなければ、長続きしません。
お子さんの「好き」や「得意」を見つけ、そこから学びを広げていくアプローチが長期的には最も効果的です。
今日からできる小さなステップとして、まずはお子さんの話をじっくり聞いてみませんか?「なぜ勉強が難しいと感じるのか」「どんなサポートがあれば助かるか」など、お子さんの視点に立つことで、新たな発見があるかもしれません。
中学生の時期は多感で難しい時期ですが、親子で協力して乗り越えていきましょう!応援しています!
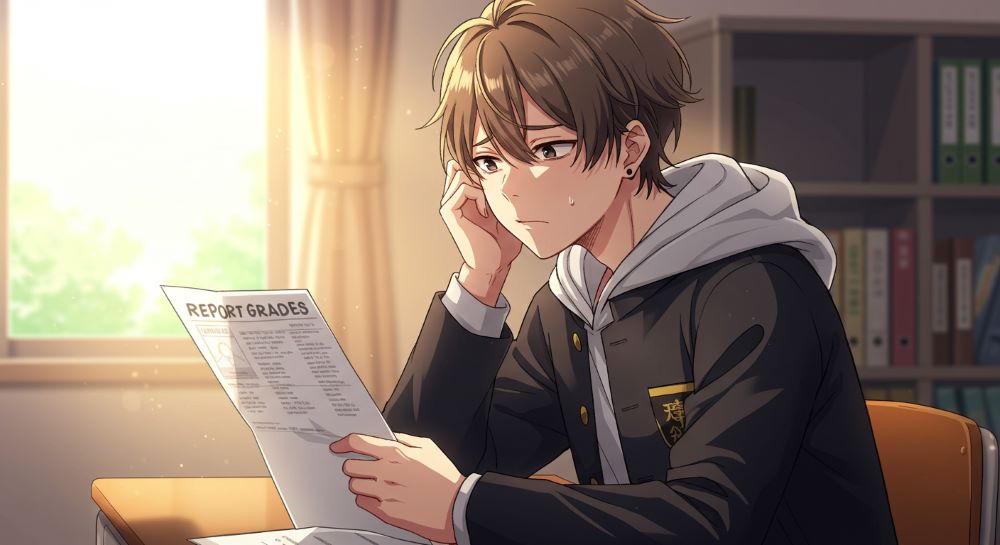
コメント